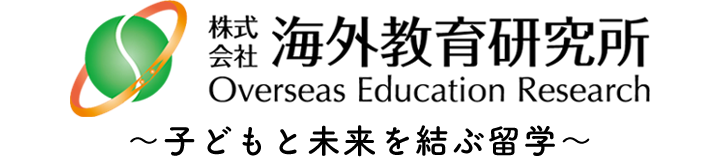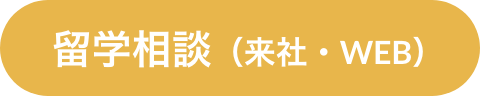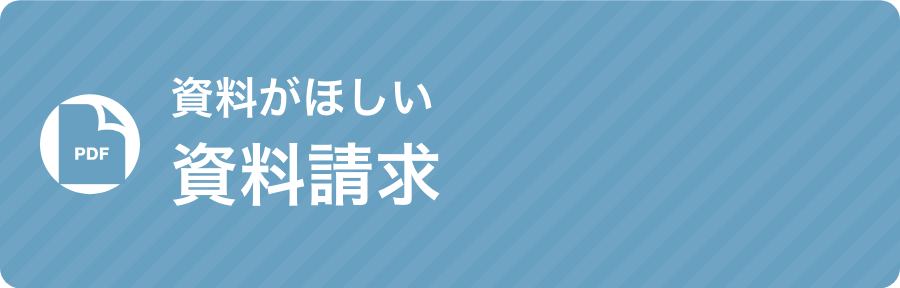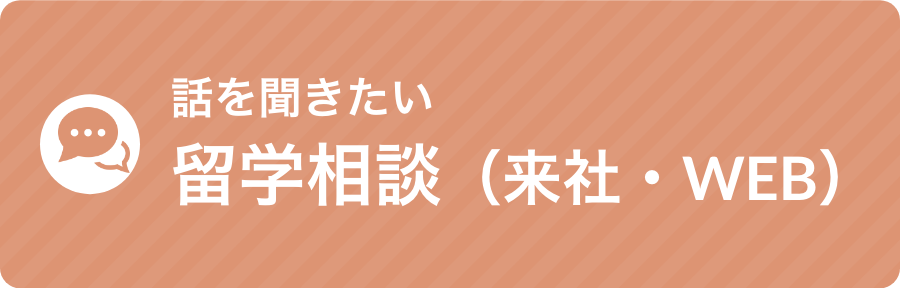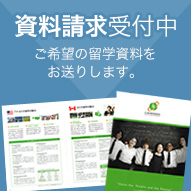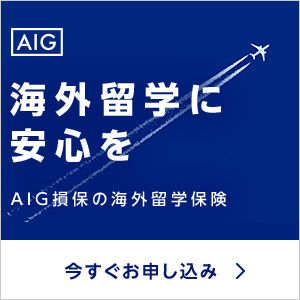🦘カンガルー便り Vol.28
こんにちは。
シドニーより古賀です。
シドニーは真夏の峠を越えて、少しずつ日中の気温が20度台の日も多くなってきました。オーストラリアは暑い国、という印象をお持ちの方もいらっしゃるかと思いますが、年間を通して湿度も気温も高めのゴールドコーストなどがあるクイーンズランド州と比べると、シドニーでは真夏と感じる期間は意外にも長くはありません。春や秋の過ごしやすい時期が非常に長く、私にとっては気候一つをとっても長く住みたくなる理由のひとつです。
さて、今回のテーマは息子たちの「日本語力」です。我が家の息子たちはオーストラリアに到着したとき、長男は7歳(小学2年生)で現在12歳(中学1年生)、次男は4歳だったのが9歳(小学3年生)になり、次男はオーストラリア生活が日本でのそれを上回りました。前回の記事で触れた通り、兄弟間での会話が100%英語になってからすでに1年が経ちました。5年目にして彼らの脳内では「子ども同士でなら英語の方がラク」に切り替わったということです。移住当初、在留年数が長いたくさんの方から聞いていたこの現象が、日本生まれである程度日本語の基礎があり、かつ親とは日本語で話している我が家の息子たちにも起こることになるとは、正直想像していませんでした。子どもたちの柔軟な適応力を実感する一方で、彼らが日本語を使う機会が親との会話だけに限られてしまっていることが、非常に残念に感じています。案の定、次男は文章の構成は何とか日本語の形を保っていますが、出てくる単語は英語まじりで私にしか通じない話し方になっています。例えば、「リンゴを切って」と言うところが「アップルをカットして」となってしまうのです。(そのうちふざけて「アップルをカッて~」と、どんどん崩れていってしまっています。)
このままでは息子たちが日本の祖父母や友人との会話ができなくなるだけではなく、私自身が息子たちと深い会話をできなくなってしまう、と危機感がいっきに押し寄せてきたことで、私はこれまで全くその必要性を感じていなかった「日本語教育」についてリサーチを始めました。まずは、私自身が教えることは継続の努力に自信がなく早々に選択肢から排除されました。
少し長くなってしまいましたので、この続きは次週お楽しみに。
【おまけ】子どもたちの長い夏休み中に訪問した場所のいくつかを写真で紹介します。